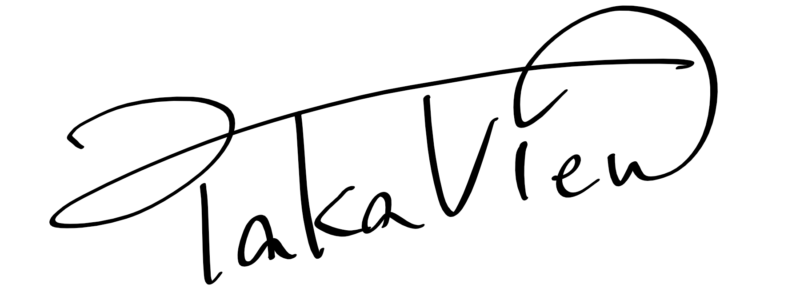みなさん、マネジメントという言葉を聞いて、何を思いますか?
私は少し前に、二瓶正之さん著の「徹底的にかみくだいたドラッカーの『マネジメント』『トップマネジメント』」を読み終わりました。
マネジメントについて知りたい方への入門書に最適だなと感じましたので、今回はこの本の魅力についてお伝えしたいと思います。
マネジメントってなんだ?
人事制度の整った会社で働かれている方ならば、階層別研修制度や昇任(昇格)試験、1on1面談など、社員の勤労意欲を高めるための制度や若手の定着率を向上させるための制度があるかと思います。
そして課長や部長といった中間管理職には、そのような人事制度を上手く活用してマネジメントをするスキルが求められます。

ところが、ネットや職場で「この会社にはマネジメントをできる人がいない」という声を聞きます。私自身、「あの人は全然マネジメントができない」と思うことはあります。
しかし、ふと思ったことは、「一体マネジメントって何だろう?」という素朴な疑問です。一言にマネジメントといっても、単に人を管理する(=manage)ということなのでしょうか。
マネジメントをもう少し詳しく学んでみたいと思い、たどり着いたのがこの本です。マネジメントといえばドラッカー。ただドラッカーが執筆した本は結構難解なようで、また複数冊あることから、できれば入門用として手軽に学びたいと思いました。
答えはこの本に詰まっている
マネジメント理解のポイント
この本は初めてドラッカーについて学ぶという方におすすめできると思いました。
というのも、話のまとまりが非常にわかりやすくなっているのです。内容の構成は簡単に説明すると①~④の流れ。
②マネジャー論・・・中間管理職クラスに求められること
③トップマネジメント論・・・社長を初めとした経営層に求められること
④ドラッカー年表・・・彼がどのような人生を歩んできたか
マネジャーの基本業務
全てのマネジャーに求められる基本業務として5つ挙げられています。
それは例えば「目標を設定する」というようなものであり、このようにはっきりと業務として羅列されると「なるほど」と思ってしまいます。
マネジャーに求められる資質についても語られており、これは後天的に得られるものではなく、またマネジャーとしての絶対条件でもあります。
自分自身をマネジメントせよ
これはドラッカー自身が長きに渡って訴え続けたことです。これが有名なMBOに繋がります。
MBOとは、正式には「Management by Objectives and Self-control」であり、現在一般的に理解されているものとは大きく異なる点があります。それはSelf-controlであり、目標管理は上からのノルマ管理などではなく、自己目標管理であることです。
マネジメントとは、上司が部下に対して行うものだけではなく、自分自身でもマネジメントできるという視点に新鮮さを感じました。
トップマネジメントに求められるもの
よく役員が口にしている言葉があります。
それは「経営において人事が一番重要だ。だからこそどの会社にも人事部がある。」
この言葉がドラッカーの本を読んだからなのかはわかりませんが、この本にも同じことが書かれています。また、経営企画室およびそこに属するメンバーに求められることについて書かれており、今後の参考になることが結構ありました。
こんなこともドラッカーは考えていたんだなと、驚くばかりです。
まとめ
ドラッカーについて少しでも学んでみたいという方はうってつけです。かくいう私もその一人でしたから。
以上、TakaViewでした。