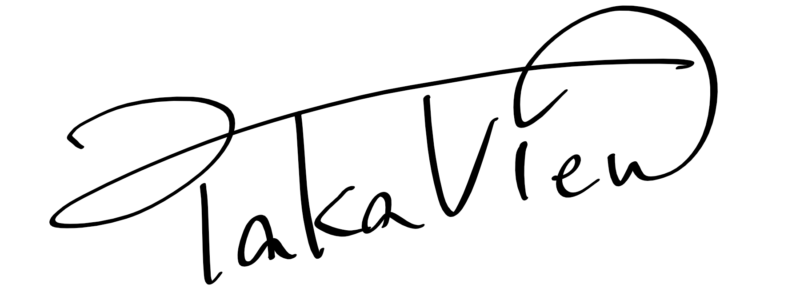インド映画『きっと、うまくいく』(原題:3 idiots)は日本でも評価の高い映画です。
ディズニー映画のように、映画の途中に踊りと歌が突如始まるというインド映画独特の構成になっていますが、内容は素晴らしいものがあります。
今回は、この映画から学べる人生のことを、背景にあるインドの社会問題にも触れながらまとめてみたいと思います。
映画におけるキーワード
All is well
本作内では、この「All is well」という言葉がキーワードになっています。この言葉をそのまま日本語に訳すと、「全て上手くいっている」という意味になります。
これをもう少し意訳して「きっと、うまくいく」という邦題にしたのでしょう。その通り、映画が進むにつれてこの言葉の意味が徐々にわかってきますよ。
主人公のランチョーいわく、この言葉は彼の村で夜回りの際に唱えられていた言葉だそう。そして彼はこのように説明しています。
バカと優秀
本作では主人公は3人います。原題では「3 idiots」となっているように、ランチョー、ファルハーン、ラージューの3人です。
脇役として、チャトゥルという学生がいます。彼は勉強熱心で、成績で1番になるために毎日何十時間も勉強していました。いわゆる「優秀」な学生です。その優秀さから、学長もお墨付きで評価していましたが、ランチョーはそのやり方は良い評価のもらうための勉強であって、本当の学問ではないと馬鹿にしていました。
本作では、自分たちのやりたいことをする「バカ」と、点数で評価されることを重視する「優秀」を対比しています。
これはある意味で、やりたいことをやっている人は世間的に「バカ」と見られがちだということを揶揄しているようにも感じます。「生きるために仕事をやってんだよ。好きなことだけで生きていけるか」というような考えです。
人の成長
この映画を全編通して一番感じられることは、主人公たちも、また悪者とされていた学長も、人間的に成長していくということです。
最終的には自分の過ちを認めて他者を理解するようになります。それはある意味で、自分を理解したということです。
3人の主人公はともに成長していきます。特にランチョーの助けが大きく、彼の人生に対する真直ぐな姿勢が周りも魅力的に見えるのです。
人は友情や恋愛を通して成長していくものなのだということがわかります。
背景にみえるインドの社会問題

自ら命を絶つ若者達
本作において、初めに映し出される社会問題は「若者の自殺」。
大学の学位取得を目指していたとある学生が、提出期限を過ぎてしまったために学長から留年を告げられます。学生は「あともう少しでできます」と留年を取り消すよう懇願しますが、学長は取り合いませんでした。その後学生は、首を吊って自殺してしまいます。
これはインドにおける競争社会(カースト)の過酷さを表現しています。映画終盤で、学長の息子も「エンジニアになれ」という一方からの押し付けにより自殺していたことが明らかになります。
「極端すぎる。所詮映画の中の話。」と思われる方もおられるかもしれませんが、全くそうではありません。現実に起きている問題なのです。
GLOBE+でこの問題について触れている記事がありますので、気になる方は是非見て下さい。
インド工科大はカーストを乗り越えるパスポート 過酷な競争、自殺相次ぐ
深く根付く「将来への不安」
主人公達をはじめ、舞台となっている大学の学生達はインドの中でも超優秀な人たち。ICE工科大学という名前で作中は登場していますが、実際にはIIT工科大学(インド工科大学)を指しているものと思われます。つまり大学は日本でいうところを東京大学や京都大学くらいのレベルです。その優秀さは次の記事を読んでいただければわかるかと思います。
インド工科大学(IIT)はなぜすごい?グーグルCEOら輩出の名門を完全ガイド
みんな賢いので何事も上手くいっていると思いきや、将来を悲観する学生が多く、点数がランキング化され落第される恐怖にも悩まされています。超優秀でも、その中でさらに優秀と落ちこぼれに分類されるのです。
また、親たちもそんな学生に期待し、成功してくれるよう願っています。学生達はそんな親の期待に応えるためのプレッシャーも感じているのです。学生は学位を取れなければ就職もできず、就職できなければ結婚もできず、クレジットカードも作れないと悲観します。
大学は本来、学問を研究するはずの場所なのに、良い成績をとって学位を取得することが目的になってしまっていると、ランチョーはしきりに訴えています。
映画から学べる人生のこと

出典:映画.com
将来ではなく自分のために今を生きる
ランチョーと親密になるまでは、ファルハーンもラージューも将来のために生きていました。工科大学に入ったからには、優秀なエンジニアになって良い企業に入って良い人生を送ってほしいという親の期待に応えるためでもありました。学生はみんな将来に成功するために生きていたのです。
就職して結婚するため、親や周囲の期待に応えるため、将来が不安で自分のために生きることができずにいましたが、ランチョーは「将来のことなんて誰にもわからない。成功は後からついてくる」と主張していました。
これはもちろん私たちにも当てはまることで、将来良い大学に入学するために、もしくは良い会社に就職するために生きている人もいるのではないでしょうか。誰かの期待に応えるために毎日頑張ってはいませんか。
ホリエモンこと堀江貴文さんが、近畿大学の卒業式でスピーチしていた時に同じことを卒業生に送っていました。何より今を必死に生きることが大切というメッセージが本作からも伝わってきます。
やりたいこと、好きなことに生きる
主人公の一人、ファルハーンはエンジニアになるべく大学に通っていますが、本当は動物好きでカメラマンになるというのが夢でした。しかし、その思いを父親に打ち明けると、エンジニアになってもらうために大学に行かせている、と憤慨します。
私は父親の考えが悪だとは思いません。父親自身は、息子に自分がしてきたような苦しい思いをさせたくないという思いがあったのだと思います。
それでもファルハーンは折れず、今まで良い子で生きてきたから、今回だけはわがままを聞いてほしいと父親を説得しカメラマンになる夢を認めてくれます。世間一般的に評価されるエンジニアという道ではなく、カメラマンという道を選んだのです。
このように人生にはある程度固まったレールがあり、そこから外れるようなことは嫌煙されます。社会に出る前の学生時代に成功モデルが刷り込まれてしまうのです。これはインドに限った話ではなく、日本でももちろん当てはまることです。
どんな状態を持って成功と言えるかは自分の価値観次第だと私は思います。やりたいことをしていない自分をきっと将来後悔するだろうとファルハーンは考えたのです。
このシーンの時、心のどこかで羨ましいと思ったなら、あなたは今やりたいことができていないのではないでしょうか?
ところで映画の感想は?
私の正直な感想は「とても面白かった」です。インド映画自体をしっかり観たことがなく、本作が初めてでしたが、ハリウッド映画にも劣らない内容の素晴らしさを感じました。
急にミュージカル的に歌とダンスが始まるのも新鮮でした。「インド映画でおススメできるものは?」と聞かれれば、間違いなく私はこの映画を勧めます。
気になった点を挙げるとすれば、「何事も上手くいきすぎでは?笑」という気持ちでした。映画なので気にしていたらしょうがないということはもちろんですが。これくらいわかりやすい方が視聴者的には良いかもしれませんね。
まとめ
人生に何かしらのモヤモヤを感じているなら、必ず得られるものがあるはずです。
以上、TakaViewでした。